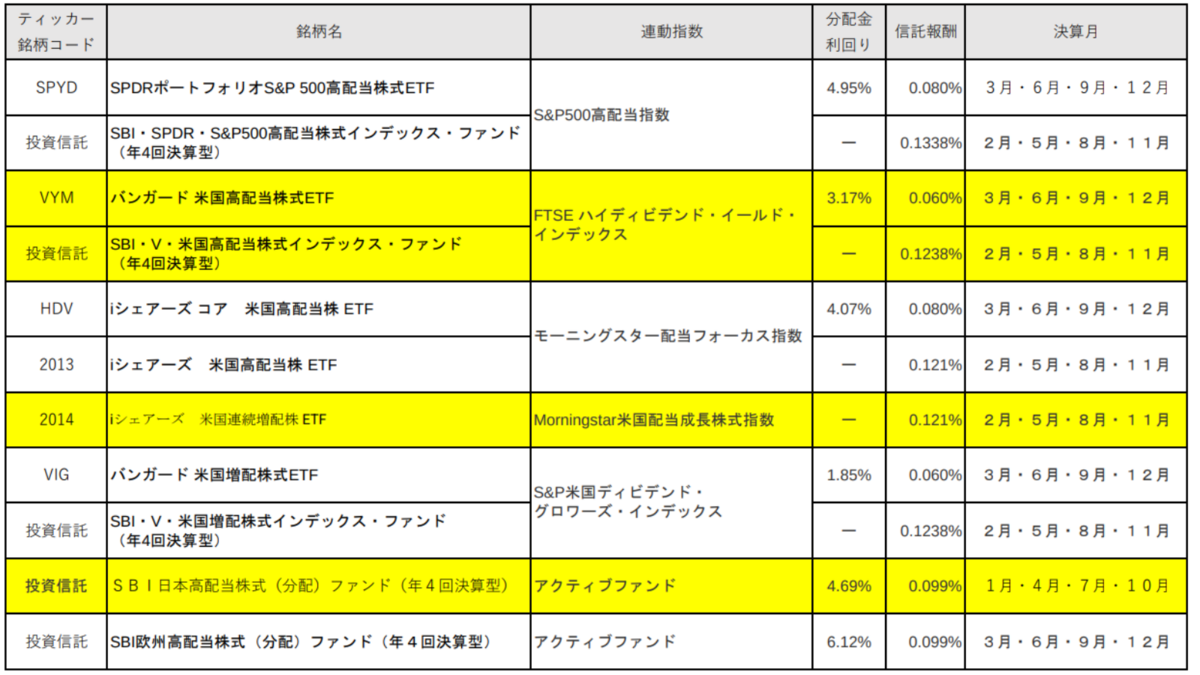NASDAQ100よりもさらにハイテク銘柄に尖った投資を可能にする投資信託の代表選手といえば「FANG+」。2024年3月、「FANG+」に対抗する投資信託が立て続けに誕生しました。1つ目は東証ETFの2244の投資信託版「一歩先いくUSテック・トップ20インデックス」。FANG+が10銘柄の均等荷重なのに対し、5つのセクター計20銘柄に時価総額加重平均で投資。もう一本は愛称「マグニフィセント・セブン」。その名の通り、今を輝く大型テック企業7社に均等荷重で投資。銘柄数も絞られるのでリスクも大きいですが、大型テック企業に重点投資したい人にとっては魅力的な投資信託。投資対象の重複が大きいので当然似た値動きになりますが、20銘柄(時価加重平均)・10銘柄(均等荷重)・7銘柄(均等荷重)と、現在伸びているテック企業のさらなる発展を期待するのであれば、余計な銘柄を削ぎ落とした「マグニフィセント・セブン」も人気を集めそうです。リスクや信託報酬を考えると「一歩先いく」が一歩リードしそうな気配ですが、今後人気を集めるのがどの投資信託になるのかも注目していきたいと思います。
【FANG+】
主要銘柄「FANG」(Facebook、Amazon、Netflix、Google)+6銘柄(アップル、マイクロソフト、エヌビディア、テスラ、スノーフレイク、ブロードコム)の合計10銘柄に均等荷重で投資する。リバランスは年4回。新NISAの「つみたて投資枠」「成長投資枠」に対応。
【一歩先いくUSテック・トップ20インデックス】
東証ETFの2244(グローバルX US テック・トップ20ETF)の投資信託版。主にナスダックに上場する米国を代表するテクノロジー企業20社で構成(中国、香港に本社がある企業は除外)。以下の5つの各セクターの上限を25%、1銘柄の上限を8%とし、条件内で時価総額加重平均。リバランスは年2回。
(5つのセクター)
・自動化(ロボティクス)
・クラウド
・コンテンツ/プラットフォーム
・eコマース
・半導体
米国大型テクノロジー株式7銘柄(Amazon、Apple、Google、NVIDIA、Tesla、Microsoft、Meta)に均等荷重で投資。リバランスは半年に一度。